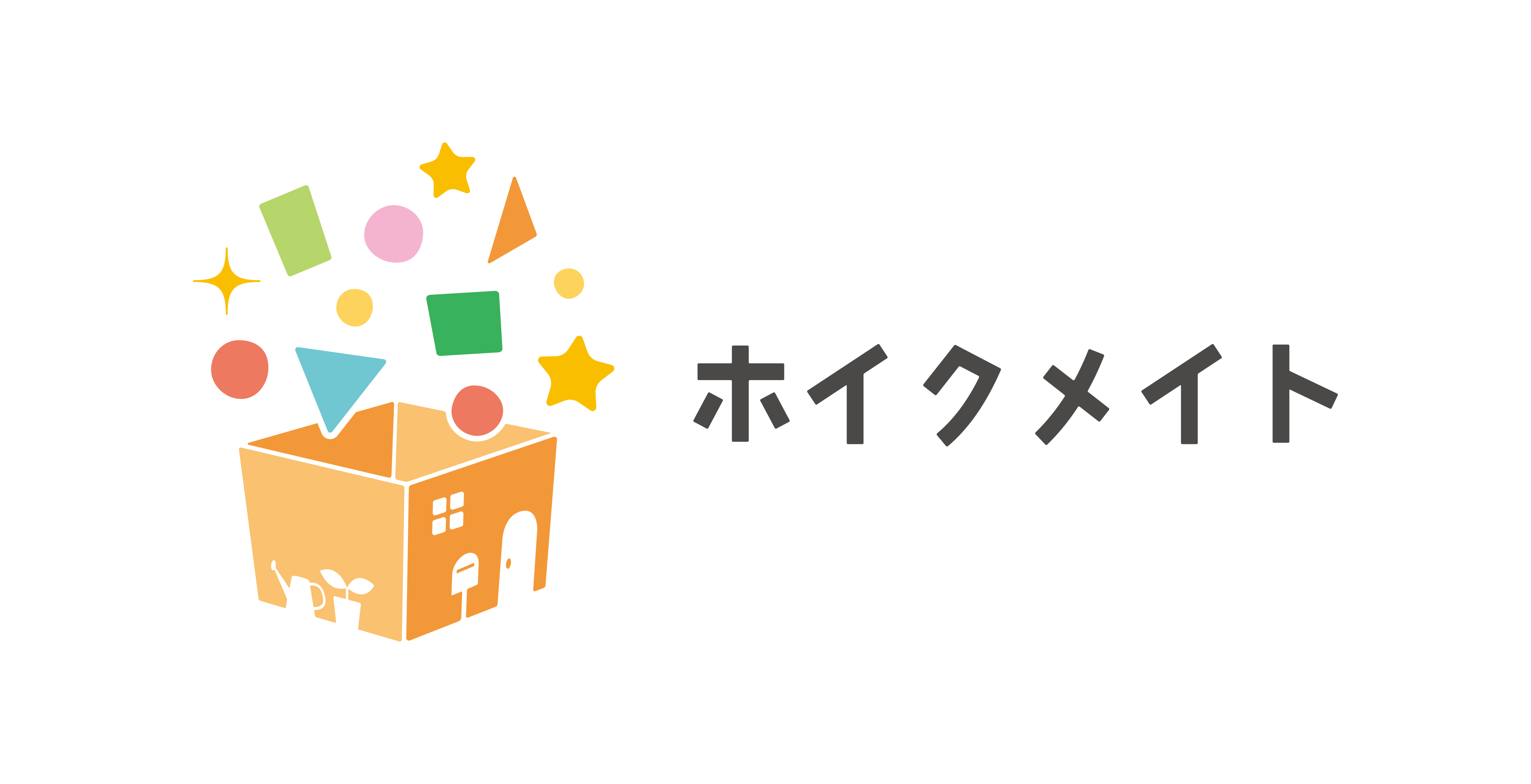2026年の「こども誰でも通園制度」による影響は?
こんにちは!一時預かり・託児所開業サポートの油谷です。
今回は『2026年の「こども誰でも通園制度」による影響は?』についてお答えしていきます。
「こども誰でも通園制度」の特徴および保育施設が受ける影響を考えていきます。

2026年度からの本格的な施行が予定されている「こども誰でも通園制度」。
保護者が働いていなくても、子どもが生後半年から満3歳未満であれば、月10時間までは保育園へ子どもを預けられるようになる制度です。
保育園はこれまで、保護者が働いていたり、病気や介護といった事情があるなどして、認定を受けた家庭のみが利用できる施設でした。 しかし、制度施行後はより多くの家庭が、時間単位で保育園を利用できるようになるわけです。
「こども誰でも通園制度」が策定された背景には、次のような考え方がベースとしてあります。
- 保育園を利用していない子どもにも、子ども同士で遊べる機会を提供する
- 育児疲れの状態になっている保護者をサポートする
- 子育てに関する悩みを相談できる相手がいない保護者をサポートする
非常に有意義な制度だといえますが、受け入れ側である保育士からは、不安の声もあがっています。
保育園を運営する事業者としては、そういった声に耳を傾け、対策をしていくことが求められます。
参照元:政府広報オンライン|こども誰でも通園制度(https://www.gov-online.go.jp/article/202408/tv-5487.html)

⚫︎一時預かりとの違いは?
「こども誰でも通園制度」とは別に、国が運営する「一時預かり事業」というものがあります。「一時預かり事業」を利用すれば、仕事や病気など、保護者に特定の理由がある場合にのみ子どもを預けられます。
「こども誰でも通園制度」の役割に似ているため、本当に両方必要なのだろうか、と感じる方もいるでしょう。けれども、実際には相違点が多数あります。相違点は次のとおりです。
【こども誰でも通園制度】
- すべての自治体で実施予定
- 生後半年から満3歳未満の子どもが対象
- 各家庭がライフスタイルに合わせて利用できる
【一時預かり事業】
- すべての自治体が実施しているわけではない
- 保護者の事情で一時的に保育が困難な子どもが対象
- 乳幼児に必要な保護を行う

こども誰でも通園制度でお子さまをお預かりするのは保育士さんです。
私が実際に一時預かりを運営していく中で感じたことは保育士さんは子どもは大好きだけれど、保護者の対応は学んできていないので、苦手意識がある方が多いということです。
保護者さまの気持ちに寄り添うことこそ一番大切なことであるにも関わらず、できない方も非常に多くいらっしゃいます。
ですので、認可外保育施設は保護者さまとのコミュニケーションに力を入れます。
要望や質問に耳を傾け改善し、また、子どもの状況をしっかりとシェアすることが大切です。
そうすれば、保護者さまはただ預かって欲しいだけではないので、自園から離れなくなりますよ。